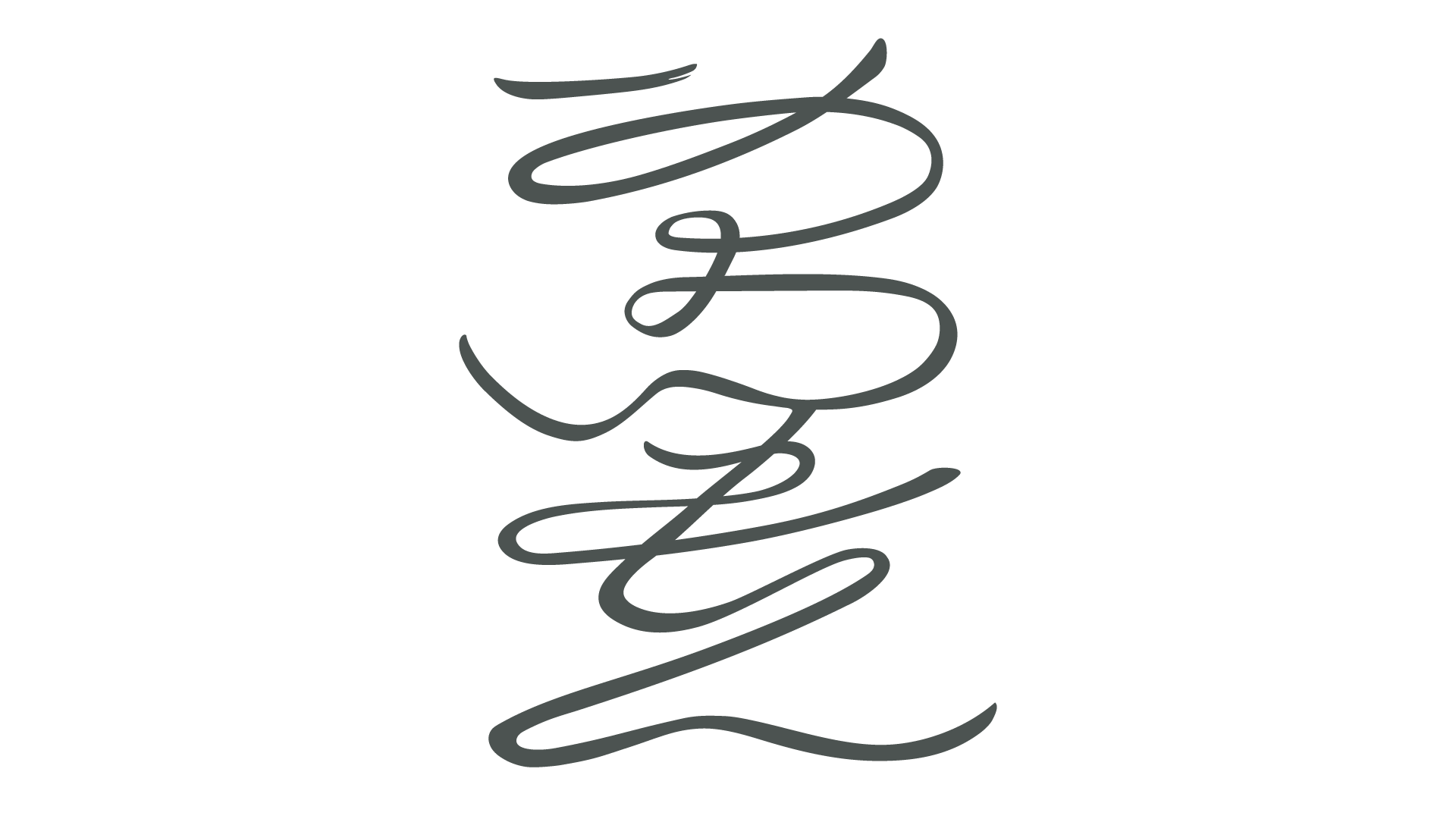公家や武家が主役だった時代に変わり、庶民が文化の担い手となった江戸時代。和菓子や洋菓子も江戸時代なくしては、今のような形にはならなかったでしょう。
唐菓子や南蛮菓子を真似ながらつくられていった和菓子と洋菓子は、唐や南蛮のそれとは似て非なるものへと切磋琢磨し、日本独自の菓子文化「お菓子」となりました。
それは、日本人が得意とする「〜気(げ)」「〜らしい」「〜ぽい」のような「見立て」の表現手法が大きく作用したもの。対象の一歩手前で留め対象へとせまる手法は、大きな壁をつくらずに障子のようなささやかな仕切りとして完成される。そこに生まれる間(あわい)は、奥ゆかしさとともに大切にされてきました。
表現が文化となると往々にして縛りもきつくなりますが、江戸時代のたのしさは、まだ文化となる少し前の自由さにあると考えます。
あわいもんの紙背にあるのは江戸時代。
“手作業でつくれるだけの物と量”を美学とします。ここに集うのは、一つの括りに縛られない、領域と領域の間で、不要と要のどちらにも寄らず揺めき存在するもの。例えば、菓子と玩具、置物と道具、西洋と東洋といったものの間に。
およそ一年に一度都内に出現するあわいもんの“場所”は、家、店、展示室のどれでもないものです。主役と脇役の関係をつくらないことで生まれるやわらかさが息継ぎとなる、そんな場所を目指します。
お店の開店時期、詳細はinstagramにてお知らせいたします。
(当サイト内Updatesでもたまにお知らせしております)
オンラインストアでは一部作品をご紹介しています。
https://www.instagram.com/awai_mon/?utm_medium=copy_link
店主 土谷未央